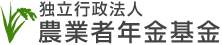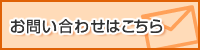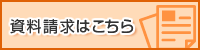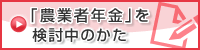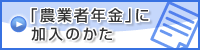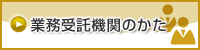本サイトにはPDFのコンテンツが含まれております。
PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
同ソフトをお持ちでない場合は、Adobe社のサイトからダウンロード(無償)してください。
加入者・受給者の声
加入者の声

T・Sさん(40歳)
横須賀市津久井のミカン農家、志村農園のT・Sさんは農園で雇う従業員を農業者年金に加入させている。
現在4㌶の畑で5~6種ほどのミカンをローテーションで作る。スーパーとの直接取引をメインに観光農園も営むT・Sさんは、ミカンの一層の規模拡大を進めながら、加工やその他、通年で収入を確保するための新規事業の開拓など、新たな分野にも積極的にチャレンジしている。そのような状況で近年「農家としての力をつけたい」と色々な仕事をこなせる若い人材を確保した。
従業員に対しては「せっかくうちに来てくれたのだから」と、サラリーマン並みの昇給制度や年金加入を模索。福利厚生の一環として農業者年金制度を活用し、保険料は給料に上乗せした。
従業員の一人、S・Kさん(24歳)は昨年5月に農業者年金に加入した。加入に際しては、農業者年金だけではなくイデコやその他、類似の制度の選択肢の中から、S・Kさん自身が農年を選択した。S・Kさんはその決め手を「農業者年金が一番シンプルで、放っておいても最適な運用をしてくれるところ」と話す。
「自ら調べて選ぶことで、制度の理解にもつながるし、加入に対する満足度も上がる」と話すT・Sさん自身はまだ未加入で「今後は少し資金に余裕ができるので、夫婦2人で満額で加入します」と笑顔を見せた。
(全国農業新聞・関東版 2024年10月4日号掲載記事より抜粋)

M・Fさん(42歳)、A・Fさん(43歳)夫妻
「将来、国民年金だけでは不安だった」と話すのは伊豆の国市でミニトマト26・5㌃を栽培するM・Fさん、A・Fさん夫妻。
M・Fさん、A・Fさん夫妻は、2024年3月に夫婦そろって農業者年金に加入した。
M・Fさんは、勤めていた会社を退職し、妻のA・Fさんの出身地でもある同市で、県の新規就農を支援する研修制度を利用。受け入れ農家のJ・Tさんからミニトマトの経営と技術などを学び、23年12月に就農した。現在は、A・Fさん、A・Fさんの父Y・Kさん(71)、母Y・Kさん(69)、パート従業員6人でミニトマト栽培に取り組んでいる。
農業者年金加入のきっかけは、国民年金だけでは将来が不安なこともあり、将来のためにプラスで加入できる年金を探していた際に、JA窓口に置かれているチラシを見たことで加入を決めた。
「会社で働いている時は厚生年金だが、農業者になると国民年金のみになる。他の年金と比べる中で、夫婦で加入でき、全額が社会保険料控除になることや保険料が収入に応じて変更できるので将来の備えとしても安心だと感じた。若い時に加入し要件があえば国庫補助も受けられるので、新規就農者にはおすすめ」とM・Fさん。A・Fさんも、「前の仕事を辞め、これから子どもにもお金がかかるため、加入したことで将来の備えがあり、安心して働ける。農業者年金をもっといろんな人に知ってもらいたい」と話す。
今後は、「今はまだ設備投資にもお金がかかるが、今後栽培技術を上げ農業収入を増やし保険料を増やしていきたい」と意欲的だ。
(全国農業新聞・東海版 2024年10月4日号掲載記事より抜粋)

S・Kさん(74歳)
能美市で水稲やイチジクを生産しているS・Kさん。2015年から、農業経営をしながらでも受け取ることが出来る農業者老齢年金を受給しているS・Kさんは「国民年金だけでは安心した老後は迎えられない。昨今の物価高や肥料・資材などの高騰で厳しい情勢が続いており、農業者年金に加入していて助かった」と語っている。
農業者年金に加入したのは1979年。その後、2001年に旧農業者年金の制度改正が行われた際、加入者の中には特例脱退一時金を受け取る人がいた一方、「一時金を受け取るのではなく、将来の備えのために年金として受け取る方が絶対に良いと考えていた」と当時を振り返る。02年以降の新制度についても『積立方式で少子高齢化時代に強いことや年金が終身で支払われること』が引き続きの加入の決め手になったという。
また、市町村合併前の旧根上町で長年農業委員を務め、合併後は20年4月から23年3月まで農地利用最適化推進委員、23年4月から現在まで農業委員を務めているS・Kさん。「委員として地域の農業者には農業者年金を勧めていきたい。老後資金を確保するためには国民年金の上乗せは必須であり、受給者の立場から必要性を伝えていきたい。今後はシャインマスカットやブルーベリーなど新たな作物にもチャレンジしていきたい」と笑顔で話していた。
(全国農業新聞・北信越版 2024年10月4日号掲載記事より抜粋)

M・Kさん(33歳)・K・Kさん(29歳)夫妻
筑後市でイチゴ(あまおう)20㌃を生産するM・Kさん・K・Kさん夫妻。M・KさんがJAふくおか八女の研修センターで1年間研修を受けた後、昨年、同市に移住し新規就農した。
2年目となる今年6月、夫婦そろって農業者年金に政策支援加入した。
2人の実家は非農家で、M・Kさんは大分市、K・Kさんは福岡市、共に九州の出身。2人とも大阪で働いていたが、コロナ禍となり地元に戻ることも考えた。一方で第1次産業に興味を持ち、大阪で開催された「新・農業人フェア」に参加。そこで福岡県のブースを訪問したことが就農のきっかけとなった。福岡なら、JAに研修センターがある「イチゴ」だと感じ、就農を決意した。
農業者年金制度は、地域の先輩から教えてもらい知った。自身でもユーチューブや農業者年金基金のホームページを見るなど、他の制度とも比較検討した。そのうえで保険料の国庫補助があり、積立方式であることに魅力を感じて加入を決めた。
M・Kさんは、「先輩方が繋つないできた『あまおう』を自分も繋いでいきたい。地域に恩返しができたら」と農業への思いを語るK・Kさんは「お互いの両親も応援してくれている。夫の支えになれるよう頑張りたい」と笑顔で話してくれた。
(全国農業新聞・九州・沖縄版 2024年10月4日号掲載記事より抜粋)

H・Uさん(33歳)
みやき町でアスパラガスを栽培するH・Uさんは、2020年から親元就農し、今年4月に15㌃の農地で独立経営を開始した。
農業者年金に政策支援加入したのは2022年。当時農業委員だった父Kさん(68歳)に勧められたことがきっかけだった。
Kさんは50代で会社を辞めて就農した。その後農業委員になるまで農業者年金を知らなかった。「当時制度を知っていれば入っていただろう」と悔やむ。現在は厚生年金と企業年金を受け取っており「年金がずっと来るのは本当に助かる。国民年金だけでは後々食べていけない。農業者年金は国の制度で安心できるし、若い人には保険料の国庫補助もある。早いうちから入っておいたほうがいい」と、周りの農業者にも加入を勧めている。
「国庫補助が受けられるうちに制度を知って加入できたのが本当にありがたい。農業は天候によって左右される。収入が一定ではないため将来の不安はあるが、老後は年金があると思うととても安心できる」と話すH・Uさん。
農業の大変さを知り、「両親を少しでも楽にしたい」というのが今一番の願いだ。
(全国農業新聞・九州・沖縄版 2024年10月4日号掲載記事より抜粋)

J・Kさん(58歳)、M・Kさん(60歳)、Y・Kさん(28歳)
美瑛町で水稲、小麦、豆類を中心に農業を営むJ・Kさん、M・Kさん、Y・Kさん一家。経営主のJ・Kさんは26歳のときに後継者として農業者年金に加入。42歳で経営移譲を受けてから、4代目経営主として営農を続けてきた。
J・Kさんの父親は経営移譲年金を受給しており、息子のY・Kさんも昨年から農業者年金に加入。親子3世代にわたって農業者年金に加入してきた。
「なんといっても、同一生計の家族分を含めて、支払った保険料全額が納税時の社会保険料控除の対象となるのがメリット。節税ができる面は経営者としては大きな魅力」とJ・Kさんは語る。
また、後継者であるY・Kさんは「今は父が保険料を支払ってくれているが、いずれは自分で払って将来のため加入を続けていきたい」と話す。
妻のM・Kさんは、49歳のときに農業委員に勧められ、農業者年金に加入した。それまでは女性が加入できることを知らなかったという。「もう少し早く知って加入していれば、もっと年金がもらえたのかなと思う」と当時を振り返る。
M・Kさんは現在、受給待期者で年金の受給を心待ちにしているという。「加入した当時は、自分が年金を受給するのはまだまだ先のことと思っていたが、実際にはあっという間に受給する年齢になった。専従者給与や国民年金以外に自分で使えるお金があるのは、心の余裕にもなる。年金は自分へのご褒美。まだ制度を知らない女性のみなさんには、ぜひ早いうちから加入してほしいと思う」と語った。
(全国農業新聞・東北・北海道版 2024年10月4日号掲載記事より抜粋)

Y・Aさん(40歳)
倉吉市でスイカ栽培を中心に農業を営むY・Aさんは、2024年2月に農業者年金に加入した。現在、スイカ1・3㌶、花卉のストック15㌃を栽培している。
Y・Aさんは27歳の時に、経営主である父親から経営を引き継いだが、すぐに父親が他界してしまった。その後、結婚し夫婦2人で父親から引き継いだ大玉で「シャリ感」抜群の希少な倉吉スイカを守り育てている。
地域農業を支える担い手として期待されるY・Aさんが農業者年金を知ったのは20年に認定農業者となった時だ。農業改良普及所から農業者年金制度の話を聞いてとても興味を持ったが、当時は加入のタイミングを逃してしまった。
しかし、政策支援で加入するには、今年がタイムリミットだったこともあり、農業委員会会長や事務局職員から詳しい説明を聞き、すぐに加入することになった。
Y・Aさんは投資に興味があり、他の年金商品や投資商品などと農業者年金を比較し、家族とも相談した結果、「農業者年金は、投資にはない安心材料があることや一生涯もらえて老後の備えとして必要な年金」という結論に至った。
Y・Aさんは、「夫婦2人では今の経営規模が限界。この規模を維持し、これからも長く農業ができるよう、健康に気を付けて家族と楽しくがんばっていきたい」と笑顔で話す。
(全国農業新聞・中国版 2024年10月4日号掲載記事より抜粋)

K・Tさん(50歳)
「農業者年金は国が農業を守ってくれている気がして安心」そう話すK・Tさんは、コシヒカリ2㌶とトウモロコシ9㌃を栽培する滝本ふぁーむの代表で勝山市の農業委員も務める。
K・Tさんは市役所で目にしたポスターから農業者年金を知り、定期預金や他の個人年金制度に比べ利回りが高いことなどが決め手となり2020年に農業者年金に加入した。「物価が高くなる中、農業者年金のおかげで、将来の年金が増えていくのはありがたい」とK・Tさんは笑顔を見せた。
また同市の農業者年金加入推進部長も務めている。持ち前の明るさで地元の女性農業者とも交流が多く、K・Tさんの声かけをきっかけに昨年新たに1人が農業者年金に加入した。滝本ふぁーむで手伝いをしている娘さんにも年内に加入するよう勧めている。
滝本ふぁーむでは、地元の野菜を使ったパンを作り「平泉寺のパン屋さん」として販売したり、ポン菓子や発芽玄米味噌みそ(みそルビ)の加工・販売を行うほか、地元の子どもたちを対象に2泊3日のトウモロコシ収穫体験を行っている。
4人の子育てに奮闘してきたK・Tさんは「今までは子どもたちの応援ばかりしてきたから、これからは自分の夢を実現させたい。平泉寺地区で農家民宿を開いて、宿泊客においしいコシヒカリを朝食で味わってもらいたい」と目を輝かせて今後の展望を語ってくれた。
(全国農業新聞・北信越版 2024年10月4日号掲載記事より抜粋)

M・Kさん(35歳)
坂出市府中町で果樹栽培に取り組むM・Kさん。JA香川県の農業インターン生としての研修などを経て、リタイアする高齢農家の果樹園を継承して就農2年目。農業者年金には就農後、すぐに加入した。
現在、園地1㌶で県オリジナル品種のミカン・小原紅早生のほか、日南、青島などカンキツ約70㌃を栽培する。さらにレモン10㌃を新植したほか、遊休農地を再生し、キウイフルーツ栽培に向けて土づくりの最中だ。
当面の計画は農業収入の安定を図ること。そのために品目を増やし周年生産できるように進めている。また、気象や樹体条件などに応じて潅水や施肥に対応できるマルドリ方式を導入するなどして高品質な果実づくりに挑戦している。その次は木づくり。雇用導入も想定し、作業しやすい果樹園にすることを意識している。
果樹の後継者づくりが最大の関心事。現在は、2人の子どもにも農作業を手伝ってもらい、「楽しいことを見せることが後継者づくりにつながる」との思いで奮闘する。
「やっていることがカタチになっていくこと。この時期は草刈りや摘果が大変だがどんな作業にも目的がある。それが理解できるとやりがいにつながる」と農業の魅力を語る。
「農業者年金は農業者が加入できる国民年金の上乗せ公的年金であることを研修期間中に師匠やJAなど関係機関・団体から教わり、就農すれば加入すると決めていた。保険料の納付は大変だが、将来の備えは大事。確定拠出型の積立方式であり、しっかり積み立てておきたい」と話す。
(全国農業新聞・四国版 2024年10月4日号掲載記事より抜粋)

S・Tさん(31歳)
「農業者年金の魅力は若手農業者への国庫補助や、税制面での社会保険料控除が魅力的です」と話すのは、豊岡市出石町で「タチワキゆとり農園」を経営するS・Tさん。昨年2月に政策支援加入をした。
豊岡市の非農家の出身ながら、中学時代に「職業体験」などを通じて学ぶ県の「トライやる・ウィーク」事業で、後の師匠となるY・Nさんの「ナカツカサファーム」で初めて農業を体験。Y・Nさんの有機農業に取り組む姿勢に感動したという。
以来、農業関係のアルバイトや、市の農業スクールでの学びを経て27歳で独立就農を実現。就農4年で売り上げも軌道に乗ってきた。
農業者年金への加入も、農業の師であり農地利用最適化推進委員のY・Nさんからの声かけがきっかけとなった。「身近に相談できる人と出会えたことが大きかった」と自らの就農体験を振り返る。
S・Tさんは、これから新規就農をめざす人などに「若手農業者への補助や、社会保険料控除などのメリットがある農業者年金を勧めたい」と笑顔で話す。
(全国農業新聞・近畿版 2024年10月4日号掲載記事より抜粋)

K・Oさん(36歳)
鳥取県三朝町で水稲・大豆を中心に約6・8㌶の面積で農業を営む認定農業者、K・Oさんは2023年1月に農業者年金に加入した。
K・Oさんは、2018年に31歳で親元就農。21年に34歳で父親から経営移譲を受け、認定農業者となった。これからの地域農業を支える担い手として期待されるK・Oさんを同
町農業委員会が加入推進対象者にリストアップ。職員が制度説明を行い、加入に至った。近所の加入者からも話を聞いていたことから、「自分が支払った保険料の全額が社会保険料控除の対象となるため、節税対策につながる」と魅力を話す。
「これからも無理に規模拡大はせずに、この調子で品質の良い作物を生産して、本当においしいものを届けていきたい。また、儲かったお金は農業者年金へ!老後と税金対策として絶対に入っておいた方がいい年金」と力強く笑顔で抱負を語ってくれた。
(全国農業新聞・中国版 2023年10月6日号掲載記事より一部抜粋)

M・Tさん(29歳)
滋賀県長浜市で水稲を中心に、ニンジンやマコモダケなどの露地野菜を栽培するほか、米粉の加工にも取り組んでいる、M・Tさんは2022年1月に農業者年金に加入した。
農業大学校や農業法人での研修を経て25歳で独立就農。農業者年金への加入は、現在も親交のある元研修先の農業法人の社長から「保険料の補助もあるし、社会保険料控除などのメリットも多い」と加入を勧められたのがきっかけ。「社長自身も法人化するまでは農業者年金に加入していたことから説得力があった」と話す。その後、JAや農業委員会に相談。認定新規就農者で青色申告者の場合、月額保険料2万円のうち35歳未満であれば月1万円の補助があることを知り、加入を決めたという。
「今後も祖父の思いを引き継ぎ、関わる人に喜んでもらえる農業を心掛けていきたい。未加入の方は、ぜひ加入を検討して欲しいですね」と笑顔で話してくれた。
(全国農業新聞・近畿版 2023年10月6日号掲載記事より一部抜粋)

S・Oさん(32)、M・Oさん(33)夫妻
横浜市青葉区でいちご農園を営むS・Oさん、M・Oさん夫妻は、2023年3月に夫婦そろって農業者年金に加入した。
「中学校のころの農業体験が鮮明に記憶に残っている」と話すS・Oさんは、農家出身ではないが、稲刈り後の田んぼで落ちた米を拾い集めたり、取った枝豆をすぐにゆでて食べたりしたときの体験で農業に興味を持ち、農業系の大学に進学。卒業後はJAに勤め、同期だったM・Oさんと結婚。M・Oさんの実家の農業経営を守るため昨年就農した。
S・Oさんは在職中から就農相談をしていたJA横浜の営農インストラクターから、「せっかく農業を始めるなら農業者年金の加入も考えた方がいい」と声をかけられた。
老後の資産形成が重要と感じていたS・Oさんは、信頼するインストラクターからの声掛けで加入を決意。積立方式の農業者年金を分散投資の一つとして捉え、他にも投資信託などと組み合わせることでリスクに備えている。M・Oさんも「農業者年金は小額から掛けられるのが魅力」と話す。
(全国農業新聞・関東版 2023年10月6日号掲載記事より一部抜粋)

H・Sさん(31歳)、W・Sさん(27歳)
北海道岩見沢市で水稲・小麦・大豆を中心に32ヘクタールの面積で農業を営むSさん家族。後継者のH・Sさんと妻のW・Sさんはそろって農業者年金に加入している。
H・Sさんは21歳で加入。「国民年金は将来どうなるか不安に感じた。農業者年金は自分で積んだ額に応じて受け取れ、安心だと思った」と話す。初めは保険料の国庫補助を受けられる政策支援加入を選択し、5年前に保険料額を自分で選択できる通常加入に変更している。
W・Sさんは昨年、結婚を機に農業者年金に加入した。「保険料額が変更可能と聞き、生活に合わせて変えられるのは便利」と笑顔で話す。
加入のきっかけは、H・Sさんの父で農業委員会の会長職務代理を務めるT・Sさんの勧め。T・Sさんは自身の加入期間が間もなく終わるため、その後はH・Sさんの保険料増額を考えている。「同一生計家族の支払い保険料の全額が社会保険料控除の対象となり、節税効果がある」とアドバイスする。
H・Sさんは「節税で経営にも活用できる。若い人にもっと知ってもらいたい」と話す。
(全国農業新聞・北海道・東北版 2022年10月7日号掲載記事より一部抜粋)

M・Oさん
茨城県・古河市農業委員会で会長職務代理者を務めるM・Oさんは、夫のT・0さん、長男夫妻、孫の3世代家族。2.2ヘクタールの農地でサニーレタスやグリーンロール、長ナスを生産している。
M・Oさん夫妻は2012年に農業者年金に加入。戸別訪問の際に新しく制度が生まれ変わった農業者年金の説明を聞いたことから加入した。T・0さんは「年齢的に短い期間しか加入できなかったが、年金を受給するようになってみて、やはり加入して良かったな」と実感を話す。
長男は、親元就農を契機に政策支援を受けて加入。さらに、長男の妻も結婚を契機に通常加入した。若い2人の将来を想い加入を勧めたM・OさんとT・0さんは、「自然災害や世界情勢の変化などもあり、農業をしていくなかで国民年金だけでは不安。少しでも2人の将来に備えてほしかった」と、胸の内を明かす。
(全国農業新聞・関東版 2022年10月7日号掲載記事より一部抜粋)

H・Aさん(32歳)
静岡県藤枝市のH・Aさんは、父、母の家族3人で水稲5ヘクタール、お茶40アール、野菜10アール、ブドウ2アールの農業経営を行っている。
農家に生まれ、両親が営む農業を見て育ったH・Aさん。県農林大学校(現静岡県立農林環境専門職大学)に進学し、2010年4月、卒業と同時に就農した。「父から技術を学び、農業の厳しさ、楽しさを日々実感している」という。
H・Aさんが、農業者年金に加入したのは、今年4月。農地利用最適化推進委員から勧められて興味を持ち、さらに詳しい説明を農業委員会職員から聞いた。22年1月から改正された新制度を使って、県内で初めて保険料月額1万円で加入した。
「長い期間加入した方が運用益もあり、年金原資が増えていくと思う。将来の支えができ、安心感を持った」とH・Aさん。さらに「支払った保険料の全額が社会保険料控除になり節税となるのでありがたい」と話す。
(全国農業新聞・東海版 2022年10月7日号掲載記事より一部抜粋)
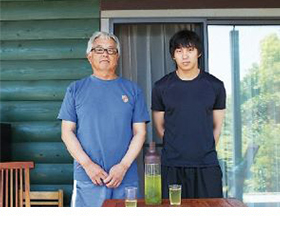
S・Sさん(62歳)、H・Sさん(25歳)
宮崎県高鍋町で茶6ヘクタールを栽培し、加工販売しているSさん一家は、3世代で農業者年金に加入している。
S・Sさんは、父が経営移譲年金を受給開始したのを機に、旧制度の農業者年金に加入。その数年後に制度の大改正が行われ、周囲では脱退する人も多かったが「いま辞めて少ない脱退一時金をもらうより、将来年金として受け取ろう」と新制度の農業者年金への継続加入を選んだ。
息子のH・Sさんは、埼玉県の製茶会社に勤務しながらお茶づくりを勉強し、昨年2月にUターン。就農したばかりで年金のことはまだ考えていなかったH・Sさんに、将来への備えとして農業者年金を勧めたのは、身をもって制度を理解しているS・Sさんだった。
積立方式で運用益も付くことに加え、S・Sさんからの「国が保険料を補助してくれる制度を利用しないと損だ」という後押しがH・Sさんの政策支援加入につながった。
父から子へ、そして孫へ、お茶づくりの技術伝承とともに、農業者年金のバトンも引き継がれている。
(全国農業新聞・九州・沖縄版 2022年10月7日号掲載記事より一部抜粋)

T・Kさん(58歳)、D・Kさん(22歳)
秋田県横手市清水町のKさん親子は地域農業を担う専業農家だ。
2015年に清水町集落の農家17戸で設立した農事組合法人清水町の代表理事でもある父Tさんは、42㌶の経営面積を持つ同法人で主に米や加工用キャベツの生産・販売業務に携わる。
認定農業者として個人経営も行う父Tさんは、節税と老後生活の安心を求めて17年3月、農業者年金に保険料月額6万7千円の最高額で通常加入した。
息子のDさんは、山形県立農林大学校を卒業し18年4月に就農。現在、スイカの秋田県オリジナル品種「あきた夏丸」の栽培などに取り組んでいる。これからの農業経営では社会保険の充実が大事だと考え、父Tさんと家族経営協定を締結し、20年1月に政策支援区分3で青色申告を行う認定農業者の直系卑属(後継者)として農業者年金に加入した。
二人の加入には、横手市の職員で農業委員会にも勤務経験がある父Tさんの妻(51)や農業委員さんの勧めが大きかったという。
法人の代表として地域農業を支える父Tさん。一方、息子Dさんは農林大学校時代に知り合った妻(22)と結婚し、8月にはパパになって経営規模の拡大に意欲を見せる。K家のこれからを農業者年金がしっかり支えていく。
(全国農業新聞・北海道・東北版 2021年10月8日号掲載記事より一部抜粋)

H・Yさん(40歳)
群馬県高崎市で両親と共に果樹園で働くHさんが農業者年金に加入したのは2020年。
Hさんに農業者年金の加入を勧めたのは、Hさんの父(66)と母(66)だった。Hさんの父が営む180㌃の果樹園では、ブルーベリー、プラム、桃、ネクタリン、梨など、多品目の果樹を生産。直売所や小売店で販売し、宅配もする。
Hさんの母は「私たちは年金に加入できる年齢のとき、経営が安定しなくて入りたくても入れなかった」と当時を振り返る。「娘には将来不安な思いをしてほしくない」という思いがあった。
Hさんの父は、農業委員会事務局から税制の優遇や、支払った保険料を農業者年金基金が手堅く運用していることなど農業者年金制度の説明をしっかり受け、娘へ伝えた。
Hさんは、26歳までは会社勤めをしながら休日に果樹園を手伝っていたが、飲食店を営む夫との結婚を機に退職し、就農した。国民年金の第1号被保険者となったHさんは「両親から勧められ、2人の子供もいるし、老後生活の安定を望んで加入した」と話す。昨年、父の長年の夢だった直売所の建て替えが完了した。店頭でHさんは一手に販売を担っている。
農業者年金に加入し、新鮮でおいしい果物の魅力を多くのお客さまに届けるため、Hさんの新たな挑戦が始まった。
(全国農業新聞・関東版 2021年10月8日号掲載記事より一部抜粋)

K・Eさん(24歳)
イチゴ20㌃と水稲5㌶を家族で営む岐阜市のK・Eさん(24)は、農業委員を務める父から農業者年金への加入を勧められ、今年5月に政策支援加入した。
きっかけは、父から「農業を続けるのなら、老後の備えとして国民年金の上乗せ年金を」と加入を勧められたこと。Kさんは、父も農業者年金に加入していたため、制度に対して安心感があったという。生涯にわたり年金を受け取ることができ、仮に80歳前に死亡した場合でも、死亡一時金があることから、加入を決めた。
加入にあたっては、父と農業委員会事務局から詳しく説明を受けた。後継者として家族経営協定を結んでいたこともあり、保険料に国庫補助のある政策支援加入を選択した。
Kさんは「若いうちに加入することで、長い期間保険料の補助を受けられる。早めに制度を知って良かった」と感じている。加入を勧めた父も、自分と息子Kさんの保険料を一括して支払うことで、全額が社会保険料控除の対象となり、節税できることを喜んでいる。
「加入を勧められて将来設計を考えるきっかけになった」とKさん。父も「今はあまり実感がないと思うが、老後生活の備えとして農業者年金があって良かったと思う時が必ずくる」と話している。
(全国農業新聞・東海版 2021年10月8日号掲載記事より一部抜粋)

Y・Hさん(41歳)、T・Hさん(40歳)
広島県世羅町上津田でキャベツ2㌶を栽培するY・Hさん(41)と妻のTさん(40)は、農業を生涯の仕事と位置付け、老後の生活資金を積み立てるため2016年9月に農業者年金に加入した。
加入のきっかけは、同地区を担当する農地利用最適化推進委員さんから「農業をするなら農業者年金」「加入するメリットはあっても、デメリットは何もない」と勧められたこと。二人は、夫婦そろって政策支援を受けて加入した。
福岡県の飲食店で働いていた頃からキャベツ栽培を夢みていた二人は、冬キャベツの産地である愛知県の農業法人に就農。農業で自立する夢へと広がり、Yさんの出身地である広島県内に就農地を探すうち、キャベツの産地化と農業経営者の育成に力を入れる世羅町に活路を見いだし、就農を決意した。
「農業は自然との戦い」と話すYさん。特に近年の異常気象は脅威で「農業者年金は、いつでも保険料の減額・増額が自由にでき、災害などによる収入減に対応できる。社会保険料控除で節税もできる」と制度の良さを語り、「こうしたメリットの丁寧な説明が必要」と加入推進に対するアドバイスもしてくれた。
(全国農業新聞・中国版 2021年10月8日号掲載記事より一部抜粋)
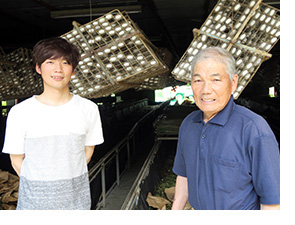
K・Tさん(79歳)、S・Tさん(26歳))
「国が保険料の一部を補助してくれるのは大きなメリットと感じた」と話すのは、愛媛県大洲市で養蚕業を営むSさんだ。2019年4月に祖父・Kさんの後を継ぐため、勤めていた会社を退職し、養蚕農家に転身。祖父が守ってきた伝統を引き継ぎ発展させていこうと、日夜技術の研さんに励んでいる。
Sさんが農業者年金に加入したきっかけは、農業委員を3期務めた経験を持つ祖父Kさんの働きかけがあったからだ。祖父Kさんは「孫が就農したから農業者年金に加入させようと考えている。説明に来てくれないか」と農業委員会に依頼。説明を受けたSさんは、「すごく良い制度だと思った」と加入する気持ちが固まり、今年5月に政策支援区分2で加入した。
祖父Kさんは、自身も年金を受給するようになって、「農業者年金は生涯にわたって給付され続ける。非常にありがたい制度だと実感している」と話す。
今年1月に祖父Kさんから経営を受け継ぎ経営者となったSさんは、「農業者は一人一人が経営者。リスク管理や今後のことを見据えて準備するのも全て自分の責任」と話す。そして、「その意味でも自分の老後の備えができたと思う。農業者年金に加入して本当に良かったと感じている」と笑顔で話してくれた。
(全国農業新聞・四国版 2021年10月8日号掲載記事より一部抜粋)

T・Kさん(29歳)
経営内容:モモ・リンゴ・サクランボ220a、水稲40a
「農業者年金の魅力は将来のための積み立てになること」と話すのは、福島県伊達市のT・Kさん。親から一昨年に経営継承した若手経営者だ。
Kさんが農業者年金に加入したのは昨年のこと。農業委員会から説明を受けたことがきっかけだった。それまで年金にはあまり興味はなかったが、将来のことを考えると、支払った保険料が運用されて自分に返ってくる積立方式に魅力を感じたそうだ。
「親から経営継承してから節税対策を考えるようになった」と言うKさん。支払った保険料が全額社会保険料控除の対象になり、将来に備えながら節税できることが加入の大きな決め手になった。
加入の手続きや制度の詳しい内容について農業委員会の窓口で説明を受けたKさんは、保険料の国庫補助が受けられる政策支援加入を選んだ。認定農業者で青色申告をしていたため、月額1万円の補助を受ける政策支援の要件を満たしていた。「少ない負担で将来の備えができるので助かっている」とKさんは話す。
(全国農業新聞・北海道・東北版 2020年10月9日号掲載記事より一部抜粋)

K牧場
経営内容:乳牛34頭、繁殖母牛50頭ほか
岐阜県関市で酪農・繁殖牛の複合経営を行うM・Kさん(34)のK牧場では、経営者や従業員の老後の備えとして農業者年金への加入を進めている。
昨年8月、家族経営協定の見直しを機に妻のYさん(25)が政策支援を受けて加入。今年7月には従業員のT・Nさん(25)が通常加入した。
飼養管理で大事にしていることは牛の栄養状態を良くし、ストレスを減らすこと。和牛の育成では採血検査により成育ステージごとの栄養状態を把握し、飼槽の残りを除去し、正確に計った量を給餌するよう作業をマニュアル化した。また、ストレスの大きい子牛の離乳では、哺乳量を少しずつ減らし、最後は空の哺乳用具のみを与え、時間をかけて離していく。こうした取り組みにより、病気が減り、出荷する子牛の評価も高まった。
農業者年金は、県農業会議の簿記講座や農業委員会の熱心な訪問で制度を知った。Yさんは「農業委員会が牛舎や自宅に何回も説明に来てくれたおかげ。個人経営には厚生年金がなく不安を感じていた頃で、Nくんも一緒に話を聞きみんなで加入しようと思った」と話す。
Mさんは「まずは長く積み立てできて保険料補助も受けられる妻に、次に、2万円の保険料の半額分を手当として支給してNくんに加入を勧めた。最後になったが自分も加入する予定です」と農業者年金を高く評価する。
(全国農業新聞・東海版 2020年10月9日号掲載記事より一部抜粋)

H・Uさん(40歳)、A・Uさん(40歳)
経営内容:ピオーネ30a、シャインマスカット20a
田舎暮らしに憧れ、農業に興味を持ち、ブドウ農家になることを目指して兵庫県から岡山県新見市に移住してきたH・Uさん、A・Uさん夫妻。
結婚して3人の子供に恵まれ、ある程度資金を確保し、子供にお金が掛かる前に移住を決意。今では消防団や後継者クラブなど移住先の地域活動にも積極的に参加し、「思い描いた生活を始めることができ、大変さもあるが充実した日々を送っている」とUさん夫妻。農園を引き継いでくれる人を探していた離農農家の圃場を紹介されて継承するなど「恵まれた状況で農業を始めることができたことはありがたい」と移住当時を振り返る。
農業者年金は2年ほど前に市役所のパンフレットで知り、30代のうちに加入すれば保険料の一部を国が補助してくれる政策支援加入にメリットを感じ、昨年7月に夫婦そろって加入した。Hさんは「保険料の額を自由に決めることができ、節税効果があり、老後の資金として期待できることが魅力的だと思った。安心感とさまざまなメリットがありお薦め」と話してくれた。
(全国農業新聞・中国版 2020年10月9日号掲載記事より一部抜粋)

K・Mさん(39歳)
経営内容:繁殖牛37頭、子牛20頭
島根県飯南町のK・Mさんは、2019年7月に認定農業者で青色申告者が加入できる政策支援区分1で農業者年金に加入した。
きっかけは飯南町農業委員会の会長から「政策支援で加入できるぎりぎりの歳であり、早く入った方が良い。説明会をするので聞きに来ないか」と誘われたことだった。
農業委員会で行われた説明会で保険料の国庫補助が受けられること、終身年金であることなど、農業者年金制度について改めて理解し、「農業は収入が安定しない職業であり、将来の貯蓄になる」と考えて加入した。
現在父と2人で繁殖牛37頭、子牛20頭を飼育している。Mさんは「農業者年金は社会保険料控除や終身年金など魅力のある年金であり、もっと早い時期に加入しておけばよかった」と言う。「保険料が自動的に引き落としになるので財布の中身が気にならない」とも話す。
これからの農業経営について「繁殖牛を現在の2倍まで増やし、従業員を雇用することを考えていきたい」と抱負を語ってくれた。
(全国農業新聞・中国版 2020年10月9日号掲載記事より一部抜粋)

T・Tさん(43歳)
経営内容:水稲15ha、ハウストマト33a
「若いうちに農業者年金に入ってよかった」と話すのは、青森県平川市のT・Tさん(43)。Tさんが就農したのは27歳の時。それまでは農業大学校卒業後に就職した農業資材販売会社の営業職として勤務していた。
就農して間もない頃は、国民年金しか入っておらず、厚生年金のような制度がないため将来への不安を抱いていたというTさん。そんな折、当時農業委員だった父親からの強い勧めで31歳の時に加入した。
加入に際しては、当時経営主であった父と家族経営協定を締結して政策支援(保険料の国庫補助)で加入した。
Tさんは7年前父親から経営を譲り受け、現在、水稲15haとハウストマト33aを経営。水稲は規模を徐々に拡大しているところだという。
経営主となった今、妻、小学生の長男と長女、両親の6人家族の生活を支える立場となる。「農業者年金は節税と老後生活のための積立ての一石二鳥。将来的に子供たちに迷惑もかけたくないので、この年金制度はとても重要だ」と考えている。
(全国農業新聞・東北版 2019年10月4日号掲載記事より一部抜粋)

~ママ友にも紹介したい~
K・Hさん(32歳)、T・Hさん(40歳)
経営内容:水稲6.5ha(うち4haは種籾)
「育児中のママでも加入できるので農業者年金に入りました」と話すのは、新潟県中魚沼郡津南町のK・Hさん(32)。
Kさんは、夫のTさん(40)とその両親と共に専業で水稲6.5haを経営。そのうち4haは種籾を作り、その他切り花の栽培にも取り組んでいる。農業者年金には、夫のTさんとその両親も加入しており、①終身で年金がもらえること、②保険料が全額社会保険料控除の対象となることなど、加入に大きなメリットがあることには理解があった。
そこで、2人の子供の子育てをしながらも農業従事日数が60日を超えていたKさんは、両親の保険料負担が終わったタイミングで、一昨年から農業者年金に加入した。
同町農業委員会で家族経営協定の締結を推奨していたことから、Tさんとの結婚を契機に家族経営協定も締結し、農業者年金の加入により安心した将来設計が立てられるようになったというKさん。
夫のTさんは同町の農地利用最適化推進委員も務めているが、Kさんは「(これから)夫婦で農業者年金がとてもいい制度であることを同じ立場のママ友にも紹介していきたい」と話す。
(全国農業新聞・北信越版 2019年10月4日号掲載記事より一部抜粋)

T・Iさん(35歳)
経営内容:水稲20ha、麦・大豆10ha、チンゲンサイ80a
「農業者年金に入るメリットはあっても、入らないメリットは何もない」と話すのは、愛知県安城市のT・Iさん(35)。
農業者年金が節税対策や将来受け取る年金が資産運用の一つになると考え、今年5月に加入した。
Tさんは、2年前から農業者年金を受給している父親から経営移譲を受け、現在、経営主として水稲20ha、麦・大豆の転作作物10haを中心に、施設の周年栽培でチンゲンサイ80aを営んでいる。
加入のきっかけは、農業委員会からの勧め。認定農業者で青色申告者だったので、政策支援加入(保険料の国庫補助)も考えたが、農業所得要件を満たしていなかったため、通常加入を選択。保険料は月額5万円で加入した。経営が苦しくなれば下げればいいし、余裕があれば増やせばいい。いつでも自由に保険料を変更できるのも魅力の一つで、加入の決め手となった。また、他の個人年金と比べても保険料が全額社会保険料控除できるという節税効果の高さも魅力だった。
農業者年金に加入した感想について、Tさんは、「将来、自分が働けなくなったら年金で暮らそうという思いもあるが、今は、まだ未来のことは見えない」と言いつつ、「このまま農業を続け10年先、20年先も米作りができる経営を目指していきたい」と意気込む。
(全国農業新聞・東海版 2019年10月4日号掲載記事から一部抜粋)

A・Nさん(44歳)、K・Nさん(45歳)夫妻
経営内容:トウモロコシ、露地野菜、水稲
夫婦で農業者年金に加入しているA・Nさん(夫44)、K・Nさん(妻45)は、木更津市で約10haの農地にトウモロコシなどの露地野菜と水稲を生産する若手農家だ。家事、子育て、農作業とフル回転のK・Nさんのやりがいは、自分たちが作った農作物を「おいしい」というお客さんの声。夏になると同農園のトウモロコシを心待ちにするお客さんが大勢訪れる。大粒で甘いトウモロコシ「ゴールドラッシュ」に魅了され、常連客が毎年増えている。
K・Nさんと農業者年金の出会いは地元農業委員会からの戸別訪問を受けた時から。
保険料の補助が受けられるという点に魅力を感じ、自ら認定農業者となり、2010年に政策支援加入した。「国民年金だけでは将来が不安」農業者年金は保険料の全額が社会保険料控除の対象になるから節税にもなるし、国からの保険料補助があるというのが一番の魅力。貯金は使うと無くなってしますけど、年金はずっともらえるから安心」と農業者年金の良さを感じている。
2人のお子さんは7歳と5歳。年金受給が可能な60歳の時にはちょうど学費が必要な年齢になる。「子供たちが大きくなればお金がかかる。子供たちの将来のためにも農業者年金で安定した生活を送りたい」と笑顔で語ってくれた。
(全国農業新聞・関東版 2017年9月15日号掲載記事より)
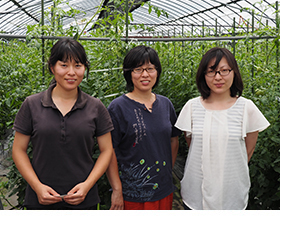
H・Kさん(29歳)、M・Kさん(26歳)、Y.Kさん(26歳)姉妹
経営内容:花苗、トマト
「農業は自営業。老後保障は国民年金のみのため、自ら老後に備えていく必要がある。上乗せ年金を考えたとき、自ら保険料を積み立てるため少子高齢化社会にも強い農業者年金を知り、両親が加入していたこともあって安心して加入できた」とH・Kさん(29)、M・Kさん(26)、Y・Kさん(26)の三姉妹。加えて両親を含めた5人全員が農業者年金の加入者である。
きっかけは、母が女性農業委員で制度にも詳しかったことが加入の後押しとなった。
3姉妹が共通してメリットを感じている所は「節税効果」と答えてくれた。特にM・Kさんは介護の仕事をしつつ、農業に従事していたため節税のためにと加入。加入時は通常加入を選択し、高めの掛け金を選択した。
姉のH・Kさんも同時期に通常加入した。「額を変更することで納税額を操作できる。節税効果が大きくまた老後のそなえもできて一石二鳥」とメリットを語る。
姉妹で一番早く就農したY・Kさんも通常加入で、3人とも通常加入を選択している。
政策支援を選択しない理由を訪ねると「自分の年金は自分で積み立て、余裕を持って保険料を支払える余裕のある経営を目指したい」と3人は話す。
(全国農業新聞・東海版 2017年9月15日号掲載記事より一部抜粋)

S・Oさん(53歳)
経営内容:水稲、水菜、キャベツ
「終身で受け取れる公的年金制度であり、掛けた保険料が全額社会保険料控除になることに魅力を感じ、加入しました。」と話すのは、S・Oさん(53)。
S・Oさんは夫の退職を機に就農した。夫がサラリーマン時代、民間の積み立ての保険に加入していたことや「老後の支えになる」という夫の勧めもあり、月額保険料5万円の形で農業者年金に加入した。
積立方式で安定的な運用であり、生涯に渡って受給できること、また80歳までに亡くなっても死亡一時金として遺族が受け取れることが決め手となり、加入を決断した。自身の両親・弟夫婦が加入していたことが、より安心につながっている。
「積立額が収入によって変更でき、全額社会保険料控除という節税効果は農業者にやさしい仕組みだと思う。50歳を過ぎ、加入期間が短くても始められる。老後を意識した時に始めるのでも遅くはないですよ」とS・Oさんは話した。
(全国農業新聞・近畿版 2017年12月1日号掲載記事より一部抜粋)

M・T さん(30歳)
経営内容:キャベツ、スイートコーン
M・Tさん(30)は就農1年目の2017年に政策支援区分2(認定就農で青色申告者)で農業者年金に加入した。
「以前から農業者年金の名前はチラシで知っていて、いつか加入しようと考えていたが、詳細な内容は知らなかった。きっかけは市の担当者と農業委員の戸別訪問だった。戸別訪問で、保険料の国庫補助が受けられること、節税対策になることに魅力を感じ、説明から一週間後に迷うことなく加入した」と話す。
M・Tさんは加入時のことを「就農1年目で不安があったが、一定期間保険料の1万円補助などにメリットを感じた。経営が安定し収入が増えれば保険料を増やしたい。毎月の保険料の支払い加入をちゅうちょしている人が多いと思うが、老後のためのお金であり、支払った分は自分に返ってくる上に、節税対策になるので加入してみたほうがいいと思う。農業者年金に入らない理由はない」と話してくれた。
(全国農業新聞・中国版 2017年11月3日号掲載記事より一部抜粋)
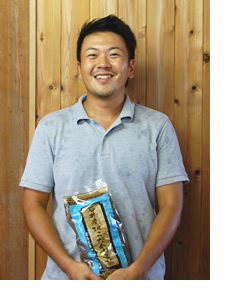
M・Iさん(27歳)
経営内容:水稲25ha、麦・大豆25ha
親元就農したM・Iさん(27)は、年金原資を自分のために積み立てる農業者年金に魅力を感じ加入した。
きっかけは、父親から「2002年1月から、制度が少子高齢時代に強い積立方式になり安心して加入できる」と聞いたこと。興味を抱いたMさんは、詳しい説明をJAに聞きに行った。政策支援があることや公的年金制度であることを知り、家族と相談し納得した上で加入を決めた。
父親が認定農業者で青色申告を受けているため、家族経営協定を結び、保険料の補助がある政策支援加入を選んだ。「若いときから政策支援に加入することで、月々の負担が少なくても老後生活に備えることができる」と話す。
Mさんは「老後のために自分で貯金するより、貯金感覚で保険料を積み立て、安全かつ効率的に運用してもらうほうが安心できる。収入が上がれば保険料を上げていきたい」と話す。(全国農業新聞・東海版 2014年9月19日号掲載記事より一部抜粋)

S・Tさん(35歳)、S・Tさん(39歳)夫妻
経営内容:ブドウ園(ハウス130a、露地70a)
S・Tさん(35)は農業者年金に2009年に加入し、妻のS・Tさん(39)も2013年に加入した。
市農業委員会のM会長に加入を勧められ、老後を考えると国民年金だけでは不安なことや、保険料全額が社会保険料控除の対象になる節税効果に魅力を感じた。
Tさん夫婦はデラウエア・巨峰・シャインマスカットなど十数種類のブドウを栽培している。夫のSさんは、認定農業者で青色申告者であれば保険料の国庫補助が受けられるメリットを生かし、政策支援加入した。子育てが一段落した妻のSさんも3年前から本格的に農業に従事。政策支援を受けることもできたが、加入期間が短いことや自分の希望で保険料額が決められることから、通常加入を選択した。
M会長は「Tさん夫婦は、農業者年金が農業者の年金であり、加入は必要だということを理解していただいた。地域特産のブドウ栽培など地域の担い手として活躍してほしい」と期待を寄せている。(全国農業新聞・中国版 2014年10月17日号掲載記事より一部抜粋)

M・Oさん(26歳)
経営内容:酪農(乳牛50頭、牧草畑8ha)
祖父の代から続く酪農家の長男として生まれたM・Oさん(26)は、2013年に農業者年金に加入した。
Mさんは両親と3人で家族経営協定を結び、月額保険料2万円のうち1万円の国庫補助を受けている。加入時の年齢は25歳で、保険料の国庫補助を制度最大の20年間受けられる。「若い時に加入すれば補助を受けられる期間も長くなるため、早く加入した方がいいですよ」とMさん。
一生続けられる仕事として酪農に魅力を感じ就農したが、「体力のある限り続けられる農業もいつかは引退する時が来る。国民年金だけでは老後の生活は不安です。農業者年金に加入しておけば、将来の基盤ができ、将来の不安がなくなる」とMさんは話す。(全国農業新聞・東海版 2015年1月23日号掲載記事より一部抜粋)

S・Kさん(32)、N・Kさん(26)夫妻
経営内容:イチゴ観光農園(70a)、キャベツ、水稲等
「政策支援加入をすれば一定期間、国からの補助を受けられるのが魅力」と話すのは、夫婦で加入したS・Kさん(32)と妻のNさん(26)。
加入のきっかけは、農業委員で農年加入推進部長のOさんから農業者年金について説明を受けたこと。Oさんは「H市のような都市部で農地を保全していくためにも、Kさん夫婦のような若手農家に長く農業を頑張ってもらいたい。農業者年金はその助けになると思って勧めた」と話す。
Sさんは認定農業者である母親と家族経営協定を結び、政策支援加入した。Nさんは通常加入。
「確定拠出型の積立方式の年金で、少子高齢化等の影響を受けず、自分で金額も決められることから安心して加入できた。二人で活用すれば、将来の生活の基盤になる」とNさんは話す。(全国農業新聞・近畿版 2014年10月17日号掲載記事より一部抜粋)

Y・Nさん(71歳)、Nさん一家
経営内容:水稲20ha、レタス2ha
2008年に息子に経営移譲したY・Nさん(71)は、旧制度と現行の農業者年金に加入し、経営移譲年金と新制度の老齢年金を受給している。息子とその配偶者も現在の農業者年金に加入している。
N家では、公的年金に加入するのは当たり前で全員が迷うことなく加入したという。Y・Nさんは「現在の農業者年金は掛け金を自分で決められ良い制度だ。」と語った。
息子の配偶者も結婚前に確定拠出型年金に加入していたため、農業者年金制度の仕組みはすぐ理解できたという。確定拠出型は保険料の枠(農業者年金通常加入では月額2万円から6万7千円)があるが、個人投資的な部分も感じられる。農業者年金基金が安全第一に運用していることから投資リスクにも不安はないという。付利(運用益)の実績にも満足しているようだ。
法人化を検討し、厚生年金に加入することも考えたが、法人化のメリットが見い出せなかったという。厚生年金に代わり、農業者年金など公的年金を中心に老後の生活費を確保できた。夫婦の趣味は海外旅行。Y・Nさんは若い頃世界一周旅行をしたことがあり、現在は夫婦で欧州や中近東、豪州など年1回の旅行を楽しんでいる。
(全国農業新聞・北信越版 2014年9月19日号掲載記事より一部抜粋)
受給者の声
M・Sさん(男性 65歳)
経営内容:メロン(ハウス43棟)
私は23歳の時に旧農業者年金に加入しました。新制度に変わる時、当時50代前半の人は一時金をもらい脱退した人がいましたが、私は同級生とともに脱退しませんでした。年金を受給するようになったいま、つくづく脱退しないで良かったと思います。
新制度にも直ぐに政策支援で加入しました。途中で亡くなっても80歳までの年金は死亡一時金として遺族に出るし、安心できる良い年金ということで加入しました。
平成27年12月に息子(36歳)に経営移譲し、平成28年1月に年金の裁定請求をしました。5月に初めて農業者年金が口座に振り込まれました。旧制度の経営移譲年金、新制度の特例付加年金と老齢年金の三つでした。全部合わせると年額で60万円余り、月額にすると5万円余りになるようです。年金はだまっていても口座に入ってきますからいいですね。
長い間、保険料を払ってきましたが、早いもので年金をもらう年になりました。経営を譲って少し寂しい気もしますが、これからも元気なうちは息子と2人でメロン作りをしていきます。息子からは専従者給与をもらっています。(全国農業図書「農業者年金加入推進事例集 vol.9」より一部抜粋)
積立貯金のつもりで加入、小遣いの足しに
K・Sさん(男性 66歳)
経営内容:リンゴ園(2.8ha)
私は30歳の時に東京での会社勤めからUターンしてきて就農しました。その時に父親が旧農業者年金に入れてくれ、保険料を払ってくれていました。
新制度に変わる時、周りでは旧制度を脱退する人が多くいましたが、私は将来年金でもらう方が良いと思って脱退しませんでした。
新制度についても、自分から積立貯金のつもりで引き続き加入しました。毎月2万円の保険料を払ってきました。
おかげで平成28年2月から新旧両制度から年金を受給するようになりました。小遣い程度の年金額ですが、何もない状況のことを考えると、国民年金にプラスされて年金収入があるのはとてもありがたく良かったです。(全国農業図書「農業者年金加入推進事例集 vol.9」より一部抜粋)
年金の一部は医療保険の掛金に
Y・Oさん(女性 67歳)
経営内容:トマト(21a)
農業者年金(旧制度)は農地の所有名義を持っていた私が加入しました。
加入して良かったことは、青色申告書を作成した際、保険料が全額社会保険料控除に回せる、つまり経費として計上できることでした。節税対策として最も効果が高いと実感し、感動しました。
新制度にも自ら望んで加入しました。賦課方式から積立方式になり、自分の老後は自分で支える制度になったことも大きな魅力ですが、保険料の全額を経費計上できる点が一番のメリットに感じられたからです。
平成27年11月から新・旧両制度の農業者老齢年金を受給していますが、年金は新しい医療保険の掛金に使っています。今まで無かった収入源があると、新しい“何か”を始める時に非常に助かると思いました。(全国農業図書「農業者年金加入推進事例集 vol.9」より一部抜粋)
孫に高校合格祝いを奮発、喜ぶ顔に感激、加入させてくれた親に感謝
Y・Fさん(男性 68歳)
経営内容:水稲(4ha)・酪農(搾乳牛40頭、育成牛40頭、飼料圃場14ha)
平成25年に長男に経営移譲し、現在は農業者年金の旧制度の経営移譲年金と新制度の特例付加年金と老齢年金を受給しています。農業者年金に加入していて本当に良かったです。孫の高校入試合格の時は奮発してお祝いをし、喜ぶ顔が見られました。加入させてくれた親に感謝しています。
長男が就農した際も、どうせ農業をやるなら農業者年金に入った方がいいと考え加入させました。89歳になった父も加入しており、「農業者年金に入っていて良かった」という気持ちを代々受け継いでいってもらえたらうれしいです。
農業者への簿記記帳指導などを行う農業簿記指導員も務めており、青色申告をしている中で、社会保険料控除による節税の大切さを常々感じています。保険料が全額社会保険料控除の対象になるのが農業者年金を勧める理由の一つです。節税を意識しないのはもったいないです。経営の状況に合わせて保険料額を変えられるのも魅力です。(全国農業図書「農業者年金加入推進事例集 vol.9」より一部抜粋。)